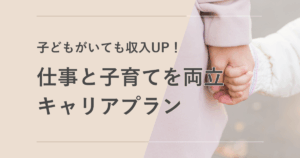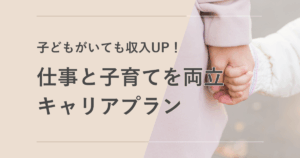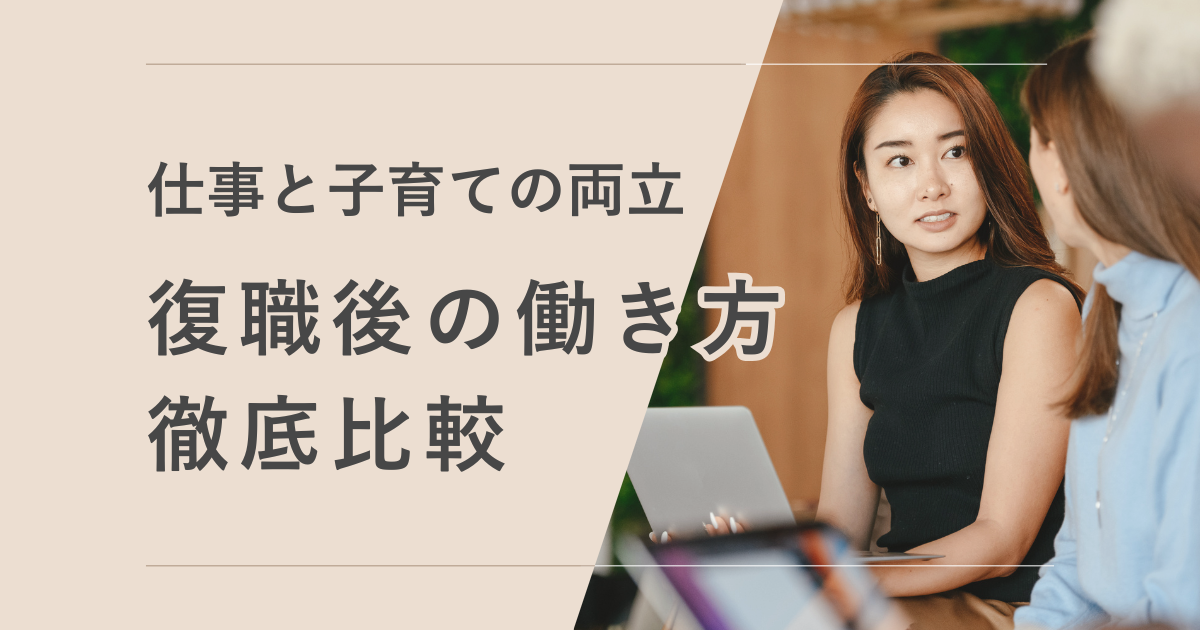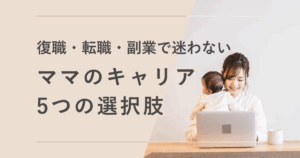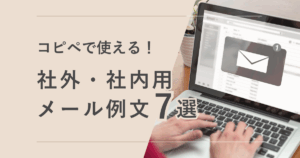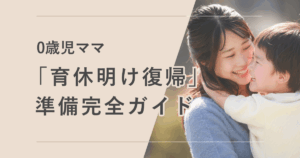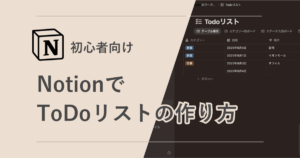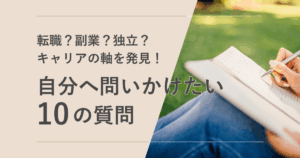育休明けが近づいてくると、多くのママが直面するのが「復職後の働き方をどうするか」という悩み。
フルタイムで働けるのか、それとも時短勤務やパートを選んだ方がいいのか――特に0歳児を育てているママにとっては大きな決断ですよね。
-1-e1755270625703-150x150.png) ミーパス編集部
ミーパス編集部この記事では、復職後の働き方を選ぶ際の基準をわかりやすく整理し、自分や家庭に合った働き方を見極めるヒントをまとめます。
実際に復職してみてから考えても遅くはないので、ここではそれぞれの特徴や注意点を解説していきますね。
育児と仕事の両立…働くママのよくある悩み
出産の前と後では、自分自身の体も状況も大きく異なっています。
産前は、子どもが生まれても同じように働きたいと思っていたにも関わらず、実際に子どもと接する中で、子どもとの時間を増やすため、仕事をセーブしたいと気持ちが変化するといったこともよくある話です。
実際に、indeedの調べでは、1000人のママを対象にしたアンケートで以下のような結果が出ています。
<調査結果詳細>
【正社員ワーママの両立の実態】
1. 正社員ワーママの92.2%が「仕事と子育ての両立に何かしらの困難」を抱えている。
子どもの年齢別では、第一子の年齢が0~2歳時で最も高く(96.5%)、第一子が中高生で最も低い(85.5%)正社員ワーママに「仕事と子育ての両立において困っていること」を聞くと、困っていることはないと回答した人は7.8%で、92.2%が何らかの困りごとを抱えていることがわかりました。具体的な困り事として最も多かったのは「子どもに十分に時間を割けない」(60.3%)、次いで「自分のために使える時間が持てない」(58.9%)、「精神的な余裕がなくなる」(50.2%)で、この3つは半数以上が該当する結果です。多くの正社員ワーママが、子どものための時間も、自分のための時間や精神的な余裕も持てず、悩んでいる様子がうかがえます。
(Indeed Japan株式会社“「女性の仕事と子育ての両立に関する調査」を実施。3/8〜3/10に「ありの”ママ”スケジュール展」を開催”. indeed Newsroom.2024-03-01.https://jp.indeed.com/news/releases/20240301, (2025-09-07))
実際にミーパスでは、これから子育てと仕事を両立していきたいママにアンケートを実施し、リアルな声をまとめました。
仕事と育児の両立ができるか不安
朝の支度や送迎、帰宅後の寝かしつけまで、一日の流れを考えると「時間が足りないのでは」と心配になります。(30代、第1子、一般職)
産休育休期間が長くなってしまい、戻れるか心配
少し復帰してはまた産休・育休を繰り返しており、いざ戻るとなったときに戻れるか心配です。これ以上産む予定はないので、復帰しないといけないのですが現場を離れすぎていて、状況が違うと思うので怖いです。(30代、第4子、看護師)
自分の体力が持つかどうか
産後から混合で、なるべく早く復帰するよう準備していますが、夜泣きや授乳で十分に休めず、外出する頻度も減ったので、明らかに体力の衰えを感じます。以前と同じようにフルタイム勤務に耐えられるか不安を感じることがあります。(20代、第1子、アパレル)
キャリアや収入をどう優先するか
復帰について上司と面談したところ、以前の職場(仕事)ではなく、単調な業務というか、休みやすい職場に異動と言われました。配慮してくれたとは思うのですが、正直納得がいかないです。以前の仕事が好きだったし、単調な業務にやりがいを感じられません。勝手に決められてしまったことが悲しくて、どうすれば良いか悩んでいます。(30代、一般職)


時短勤務を選ぶ基準
時短勤務とは、3歳未満の子どもの養育や介護などの理由でフルタイムが難しい従業員が、1日の労働時間を短くする働き方です。所定労働時間が原則6時間になる場合が多いです。
判断基準のポイント
- 保育園の送迎に余裕を持ちたい
- 夜間授乳や夜泣きが続いている
- 職場に時短制度が整っている
時短勤務を選ぶために必要なこと
- 就業規則を確認する:対象年齢や勤務時間の範囲は会社ごとに異なります。
- 申請のタイミング:復職の1〜2か月前までに人事や上司に相談しておくと安心です。
- 勤務時間の設定:一般的には「1日6時間」など。送迎時間に合わせて設定できるか確認しましょう。
| 項目 | 内容の例 |
|---|---|
| 利用対象 | 子どもが3歳になるまで |
| 勤務時間 | 1日6時間勤務 |
| 給与 | 基本給×勤務時間比率 |
| 申請時期 | 復職2か月前までに申請 |
時短勤務を選んだときに起こりやすいこと
- 保育園の預かり時間が短くなることがある
- 給与や賞与が勤務時間に応じて減る
- 業務内容はフルタイムと大差なく効率が求められることも
- 同僚との勤務時間がずれてコミュニケーションが取りにくい場合がある
復帰後の勤務を時短勤務にすることで、体力的な面でも復帰しやすいメリットがあります。また、比較的短い時間の保育で済むので、子どもにとってもストレスを軽減できます。
ただし、時短勤務をしたいと思っていても、業務的に難しい職種の場合や、会社の制度が整っていないために結果的に仕事量は同じで家に仕事を持ち帰らなければならないという場合もあるようです。
また、時短勤務の場合は、保育園の保育時間も時短になる場合がありますのでその点も留意しておきましょう。


フルタイム勤務を選ぶ基準
判断基準のポイント
- 家族のサポートが得られる
- 体力的に問題がない
- 職場でのキャリアを優先したい
フルタイム勤務を選んだときに起こりやすいこと
- 両親やパートナー、ファミサポなど外部のサポートが不可欠
- 朝と夕方の時間がタイトになりやすい
- 子どもの体調不良で休む際の職場調整が大変
- 夜泣きや育児疲れで疲労がたまりやすい
- キャリアは進むが家庭時間が減る傾向がある
フルタイムで復帰する際は、仕事も子育ても家事も一人で回していくのは非常に大変です。できる限りのサポート体制を整えておくとともに、子どもの体調不良時などの緊急時のバックアップ体制についても上司やパートナーとよく相談しておきましょう。
食事の準備や掃除などは、宅配サービスや代行サービスなどを活用して時間を捻出する方法もおすすめです。


パート勤務を選ぶ基準
パート・アルバイトとは、正社員と比較して労働時間が短い雇用形態を指し、働く時間や条件に柔軟性があるのが特徴です。家の近くで職を探すことで、通勤時間の短縮なども可能です。
判断基準のポイント
- 子どもとの時間を第一にしたい
- 体力やメンタルの負担を減らしたい
- 働きながらスキルアップしたい
パート勤務を選ぶために必要なこと
- 勤務日数・時間帯を確認する:週3や午前だけなど希望に合うか面接で確認。
- 社会保険の適用条件を把握する:扶養内で働く場合は要注意。
- 勤務地や通勤時間:家庭との両立のため近場を選ぶのが理想。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 勤務時間 | 午前・午後のみ、週3〜など柔軟性 |
| 収入 | 扶養内 or 社会保険加入ラインを確認 |
| 通勤 | 自宅や保育園からの距離 |
パート勤務を選んだときに起こりやすいこと
- 急なシフト調整が入りやすい
- シフト制の職場が多く急な早退・欠勤がしにくい
- 収入が安定しにくい
- キャリア形成にはつながりにくい
- 家庭時間は確保しやすい


働き方を選ぶときのチェックリスト
- 家族のサポートは十分にあるか?
- 子どもの生活リズムは安定しているか?
- 自分の体力やメンタルは回復しているか?
- 今は収入を優先すべきか、それとも家庭の安定を優先すべきか?
- 将来のキャリアプランにどうつなげたいか?
時短勤務、時差通勤、在宅、フレックス制…など、少しずつではありますが、働き方が多様化してきました。
職種によっては調整が難しい場合もありますが、あなた自身がその会社の制度を変えていくきっかけになる場合もありますので、遠慮せずに上司に相談してみましょう。
また、自分の経験を活かし、転職や独立するという方法もあります。視野を広く持ち、自分に合った働き方を模索していきましょう。
一人ではなかなか視野を広げるのが難しい…そんな方におすすめなのが、無料のキャリア相談サービスです。


専門のキャリアアドバイザーが、あなたの理想の将来像を丁寧にヒアリングし、複数の選択肢をご提案します。必要に応じて転職活動や就業後のサポートまで、長期的に伴走してくれるので安心です。
転職すると決めている方はもちろんですが、こちらの相談サービスは無理な転職を進めることが一切ないので、どうするかまだ分からない時期に、自分にできるを整理したり、自分の経験が活かせる場所や市場価値を知りたい人に人気です。
興味がある方は、以下のボタンをタップして、LINEで「キャリア相談」と送ってくださいね。
\ 子ども同伴・好きな時間にオンラインでOK/
まとめ
復職後の働き方は「正解」があるわけではなく、家庭の状況やママ自身の体力・キャリアの方向性によって変わります。
フルタイムで頑張ることが最善とは限らず、時短やパートを選ぶのも立派な選択肢。
大切なのは「無理なく続けられる形」を選ぶことです。状況は子どもの成長とともに変化するため、今の選択が未来を固定するわけではありません。柔軟に見直しながら、自分と家族に合う働き方を見つけていきましょう。
ミーパスでは、仕事も子育ても頑張る女性に役立つ情報を発信中!
「子育て中のママにおすすめの副業」や「2025年最新 収入を伸ばし子育てと両立するためのキャリアプラン」など、関連記事もぜひチェックしてみてください。