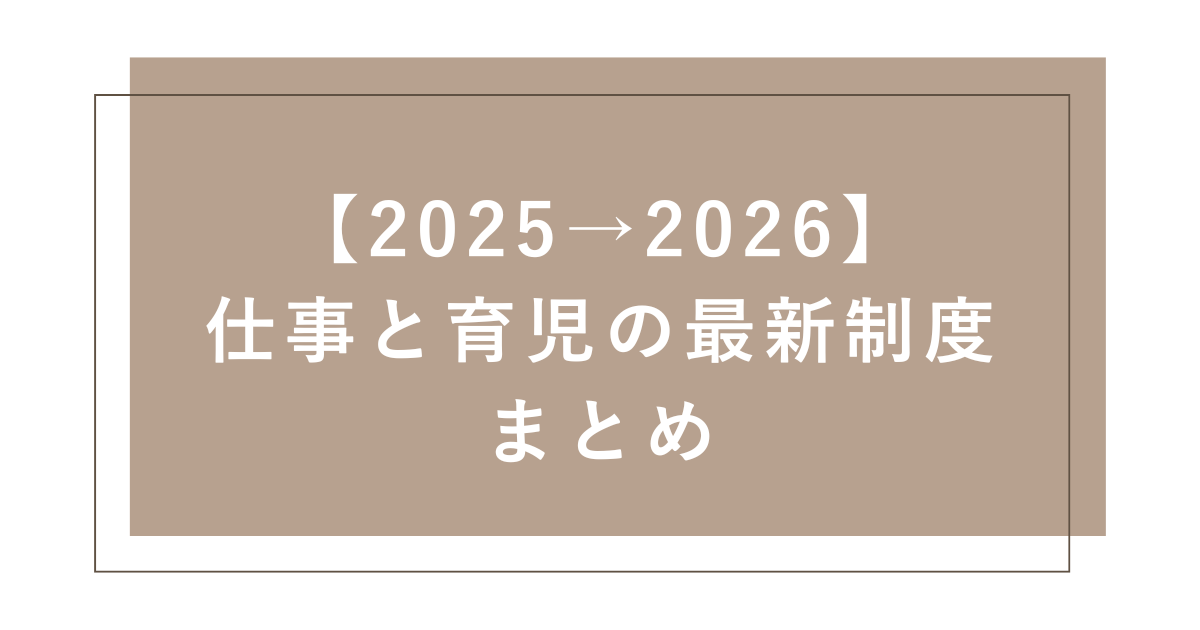2025年以降、仕事・妊娠出産・育児教育の3ステージで、さまざまな制度が拡充・新設されました。
本記事は「要点だけ早見したい」「家計への影響を知りたい」方向けに、変化点と注意点をコンパクトに解説します。
-1-e1755270625703-150x150.png) ミーパス編集部
ミーパス編集部自分自身で手続きをするものや、地方自治体によって異なり知らないと損する制度もありますので、知識として押さえておきましょう!
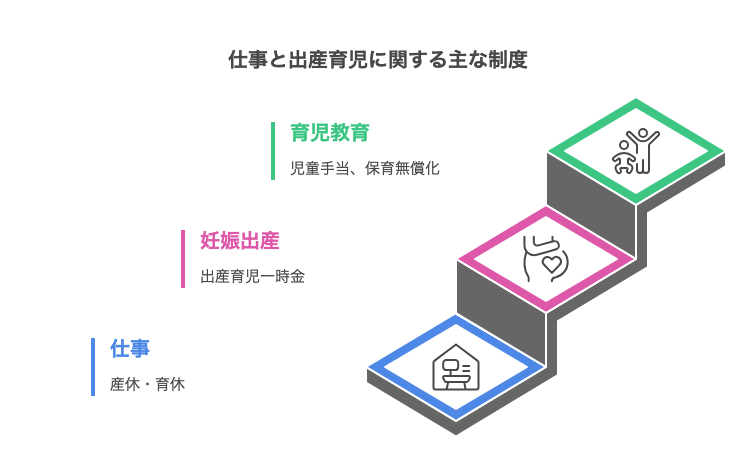
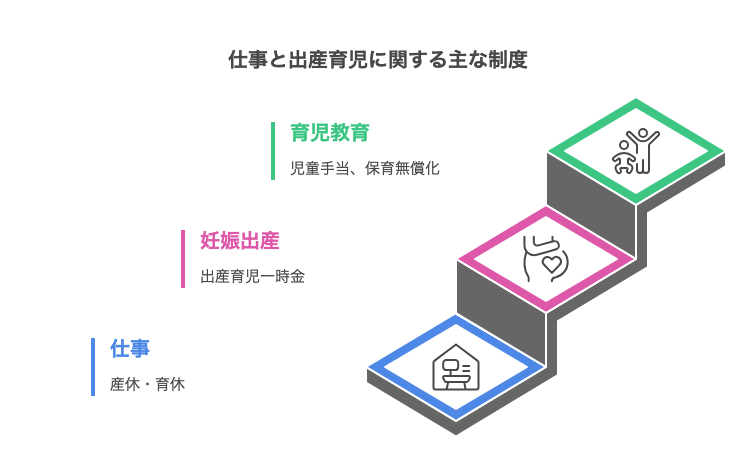
1. 仕事に関する制度(育児・介護休業法 改正 2025)
| 項目 | 2024年以前 | 2025年以降(4月・10月) |
|---|---|---|
| 子の看護休暇の対象 | 小学校就学前 | 小学校3年生修了まで、 学校行事への対応も柔軟に |
| 働き方の配慮 | 短時間勤務・時間変更など中心 | 育児期テレワークの配慮(努力義務)を明記 |
| 育休取得状況の公表義務 | 常時1,000人超の企業 | 300人超へ拡大 |
| 個別周知・意向確認 | 明確な義務の範囲は限定的 | 個別周知・意向聴取・配慮の義務化 |
育児に関する制度の主なポイント
少子化と人手不足の中で、働きながら育児や介護を続けやすくするために制度が変更されています。
育児期の柔軟な働き方(例:テレワーク配慮)、育休取得の後押し、企業の情報開示拡大は、男女ともに育児参画しやすい職場づくりに寄与します。
地方自治体が企業に対して、育休取得への支援を働きかけるという地域も増えてきました。
産休・育休などの制度が充実しているのは大企業だけという考え方が少しずつ変化し、中小企業で働く人や、初めて育休を検討するパパ・ママがより休みを取りやすい環境が整いつつあります。
注意点・デメリット
男性の育休取得取得率が少しずつ増えてはいますが、男女ともに会社内での理解を得にくい状況もあります。
- 会社側は規程整備・周知・体制づくりが必要で、準備不足だと現場に浸透しにくい。
- テレワークは「万能」ではなく、業務特性により適用限度がある。
- 従業員側も申出時期・必要書類・社内手続きの把握が不可欠。
など、制度としてはあっても実際に活用できるかどうかは別問題です。
産休・育休取得を考えている方は、会社の制度や具体的な手続きの方法などをチェックしてみましょう。
2. 妊娠・出産に関する制度(出産育児一時金 ほか)
| 制度名 | 対象者・条件 | 内容 | 2024年まで | 2025年以降 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 健康保険加入者(本人・扶養問わず) | 出産1回につき50万円を医療機関へ直接支払 | 50万円支給(上乗せは自治体任意) | 大枠は同様/一部自治体で上乗せ実施 | 病院によって出産費用は50万円超のことも |
| 妊娠に伴う医療費控除 | 妊婦本人や同一生計の家族 | 年間医療費(健診・分娩・通院交通費等)から補助分を除いた額が10万円超で控除対象 | 制度あり(申告ベース) | 基本同様/電子申告・医療費通知活用で手続き簡便化 | 補助券利用分・出産育児一時金充当分は控除対象外 |
| 出産応援ギフト (妊婦のための支援給付) | 妊娠届出をした妊婦と出生後の子 | 妊娠期・出産後に各5万円相当を支給(クーポン/現金/ポイント) | 「出産・子育て応援交付金」として全国実施 | 2025年度から法定化/自治体ごとに上乗せあり | 申請や面談が前提。自治体によって形式・額が異なる |
| 地方自治体の子育て支援事業 | 子育て世帯全般 | 引越し補助・住宅取得支援・第3子以降の保育料無償・高校生年代までの給付等 | 一部自治体で先行導入 | 2025年以降、対象拡大や金額引上げの動き | 自治体により条件や金額が大きく異なる |
| 健康保険料の免除 | 産前産後期間の被保険者 | 産前産後休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金)を免除 | 免除制度あり | 継続実施 | 免除期間も将来の年金受給額には満額反映 |
| 国民年金保険料の免除 | 第1号被保険者(自営業・フリーランス等)で出産する人 | 出産予定月の前月から翌々月までの4か月分が免除 | 2022年4月から実施 | 2025年以降も継続 | 免除期間も年金加入期間に算入 |
制度の特徴
妊娠・出産期には、まとまった費用負担を緩和し、安心して出産を迎えられるようにするために国や自治体が提供する複数の制度があります。
出産一時金は、50万円に増額され、窓口での直接支払い制度を活用することで、出産時の入院費用の建て替えが不要となり、支払い金額が軽減されます。
また、妊娠、出産に応じて国と地方自治体からの子育て支援事業も充実しとして、地域によって形態は異なりますが、チケットや現金などが支給される制度もあります
初産の家庭や里帰り出産など、資金繰りが不安な世帯にとって心理的・家計的なセーフティネットになります。
また、2026年度(令和8年度)からは、現在は健康保険が使えず自費診療となっている妊娠に伴う健診や通院が、3割負担となる方向で調整が進んでおり、金銭的な負担がさらに軽減する見込みです。
注意点・デメリット
妊婦健診、分娩は現時点では自費診療となるため、出産に伴う必要は病院によって異なります。
現状は金銭的な負担も大きく、一時金があったとしてもそれ以上に入院費用が発生したり、妊娠経過の異常によっては、入院が長期化することもあり、休職期間が延長する場合も念頭に入れておきましょう。
また、フリーランス、非正規雇用の場合は、産休育休の制度や、育児手当などが適用外となる場合がありますので注意が必要です。
3. 子どもが生まれてからの制度(児童手当・保育無償化・誰でも通園制度)
児童手当
| 項目 | 2024年9月まで | 2024年10月以降 |
|---|---|---|
| 支給対象年齢 | 中学生まで | 高校生(18歳年度末)まで |
| 所得制限 | あり | 撤廃(全世帯支給) |
| 第3子以降 | 月1.5万円(年齢区分あり) | 一律 月3万円 |
| 支給回数 | 年3回(4か月分ずつ) | 年6回(偶数月) |
制度の特徴
教育費・生活費の負担を軽減し、多子世帯や高校生世代まで支援を広げるための制度です。支給頻度が増え、キャッシュフローの平準化にも寄与します。
各制度で所得制限なども撤廃の動きが進んでおり、対象外だった家庭も活用できる制度が増えてきました。
注意点・デメリット
原則として、自分自身で役所などに申請、申し込みをする制度となります。そのため申請遅れ=受給遅れに直結しますので、出生や転入の際は早めに手続きが必要です。
自治体によって通知・振込サイクルに差があり、他県、他市区町村への転入に伴って受給が止まるケースもあるようです。手続きの漏れがないように注意しましょう。2024までとの変化(比較表)
保育無償化
| 項目 | 2024年まで | 2025年以降の動き |
|---|---|---|
| 国の基本制度 | 3〜5歳 全員無償/0〜2歳 非課税世帯 | 基本同様。多子世帯の上乗せ拡大が各地で進展 |
| 自治体独自支援 | 第3子無償・軽減は一部自治体 | 対象拡大・金額引上げの動きが広がる |
| 他制度との連動 | 誰でも通園制度は未制度化 | 誰でも通園との併用や一時預かり補助の検討が進む |
制度の特徴
就労継続と家計負担の軽減を目的に、保育料を公費で下支えする制度です。
共働き・ひとり親・非正規含むワーカーに広くメリットがあります。
注意点・デメリット
保育無償化に関しては、居住する市区町村によって細かい制度が異なります。また、認可保育園、認可外保育園など保育施設の条件によっても適応が異なりますので、詳しくはお住まいの地域の担当部署に相談してみましょう。
- 基本ルールは3〜5歳は全員無償/0〜2歳は住民税非課税世帯。地域によってバリエーションがある
- 認可外や延長保育は対象外のケースあり。自治体の上乗せも確認。
- 兄弟構成や養育環境により負担が変動(第3子無償などの自治体加算)。
誰でも通園制度(2025年度制度化→2026年度全国実施予定)
| 項目 | 2024年まで | 2025年以降の動き |
|---|---|---|
| 利用できる人 | 保育必要性認定が前提 | 認定なしでも利用可(自治体条件あり) |
| 利用時間 | 原則フルタイム枠(就労前提) | 週数回×短時間の制度化 |
| 対象施設 | 認可保育園・認定こども園・幼稚園(就労証明) | 同施設で短時間枠を新設 |
| 費用 | 自費による一時預かりが中心 | 所得・時間に応じ補助(上限設定あり) |
| 全国展開 | 国の制度なし(自治体独自) | 2025年制度化 → 2026年全国実施予定 |
この制度の特徴
こども家庭庁が主体となって行なっている制度で、就労要件を満たさなくても、月10時間の枠内で、時間単位でのの通園が可能になります。
一時預かりとは異なり、子どもの成長のために家庭にいるだけでは得られない様々な経験を得るという目的と、一定時間、こどもと離れる時間を確保することで、保護者の孤立感、不安感等の解消など育児に関する負担感の軽減につなげる狙いがあります。
フリーランス・在宅ワーク・介護や療養で一時的に支援が必要な家庭の預け先確保としても期待されています。
注意点・デメリット
新設された制度のため、受け入れ先の確保などの点で懸念点があります。今後の情報に注意してください。
- 全国一律ではなく、自治体ごとに対象・回数・料金が異なる。
- 基本は短時間・部分利用。フルタイム保育の代替ではない。
- 希望集中時は抽選・待機の可能性があり通園できない場合がある。
リアルな声と活用ヒント(エピソード)
- フリーランスは妊娠・産休・育休まわりの制度が適用外のものも多く、自治体支援・一時預かり・民間サービスの組み合わせが鍵となります。
- 会社員の場合は「育休手当はいつ入る?手続きはどうする?」という部分で困っている方が多いです。会社の手続き忘れ・遅延や、自分自身で手続きをすることを知らないことにより手当の受給が遅れる場合もあるようです。社内の担当者とコミュニケーションをとり、手続き状況を可視化しておくと安心です。
- 東京都の18歳まで月5,000円の独自給付など、子育て支援は地域ごとに独自の制度があります。出産・育児に伴う転居を計画している場合はチェックしてみましょう。
- いざという時に預けられる先の確保しておきましょう。ファミリーサポート制度・一時預かり・民間のシッター業者などは複数事前登録しておくことをおすすめします。
- 育休取得をするパパも増加傾向。ママと一緒に児童館のイベントなどに参加することでパパ友ネットワークが作れます。
まとめ
2025年以降も育児・介護休業法の改正で働き方の選択肢が広がり、児童手当の拡充や保育無償化の上乗せ、誰でも通園制度の制度化など、家計と生活の両面を後押しする制度が充実していきます。
子育て支援制度は細かく変更されたり、自治体によって手続き方法や制度の内容が異なる場合があるため、お住まいの自治体の最新情報と申請タイミングを早めにチェックしましょう。
この記事が役に立ったと思ったら、SNSでシェアをお願いします!